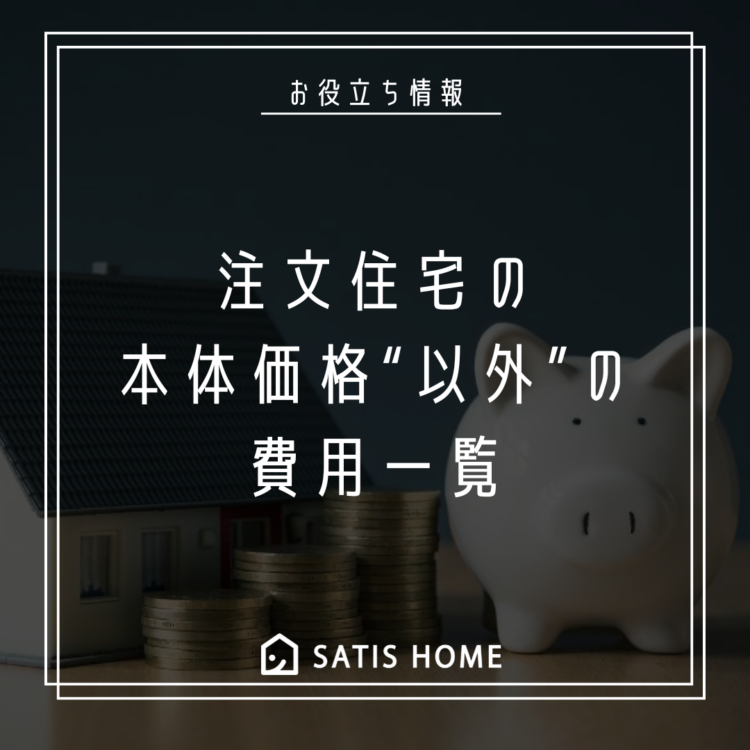お知らせ・コラム
NEWS&COLUMN


-

2025/11/04
その他
判決が確定いたしました!(今後、この裁判における判決は覆ることはありません)
最終の判決が確定いたしました!.2025年(令和7年)9月24日、名古屋高等裁判所において、最終判決が下されました。よって、これにて株式会社サティスホームと登場するお施主様(以下「相手方」といいます)
-

2024/03/31
その他
弊社を中傷する動画について、一審の判決 勝訴!
弊社を中傷する動画、それに関連する物件の裁判について結果のご報告です。弊社を中傷する動画がYouTubeで出ております。皆様にはご心配をおかけして大変申し訳ございません。このような事態になることは私

すべての記事
17